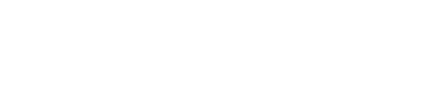永光の雛人形・ひな人形
- 美しさを追求する雛人形 -
上質なお着物、こだわり抜いた仕立て
細部まで丁寧に作られたお雛様
それぞれのひな人形が輝くようセットをいたしました
上品かつモダンでおしゃれな雛飾り
永光オリジナルのひな人形をごゆっくりご覧ください
- < Prev
- Next >
-
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「風恋 - fuuren -」
平安博翠 215,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「風寧 - fuune -」
平安博翠 213,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「花映 - はなうつし -」
雅泉 143,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「花芽 - はなめ -」
尾張屋寿翁 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「凛々 - riri -」
芳峰 198,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「萌々 - momo -」
芳峰 198,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「月のほほえみ」
柴田家千代 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「おとぎの庭で。」
柴田家千代 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「美織 - miori -」
平安博翠 176,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「千織 - chiori -」
平安博翠 176,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「結実 - yuumi - 藍いろ」
雅泉 172,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「結実 - yuumi - 茜いろ」
雅泉 172,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「和佳月 - わかづき -」
田村芙紗彦 338,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「月祈乃 - つきの -」
田村芙紗彦 323,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「京の桜時 - sakuradoki -」
平安雛幸 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「美湖月 - みこつき -」
平安道翠 312,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Raffine - ラフィーネ -」
雅泉 176,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Serein - セレン -」
平安博翠 178,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「誓和 - towa -」
平安博翠 198,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「そよ風は香り・・・」
眼楽亭富久月 横山一彦 235,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「奏よか - soyoka -」
平安博翠 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「春ゆら - Haru Yura -」
平安博翠 188,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「瑚夢 - koyume -」
平安博翠 182,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「彩夢 - sayume -」
平安博翠 173,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「HANA 踊る」
雅泉 176,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「HANA 舞う」
平安道翠 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「采 - koto -」
平安道翠 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「泉 - izumi -」
平安道翠 152,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Flora - フローラ -」
平安道翠 185,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Bloom - ブルーム -」
平安道翠 187,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Mellow - メロウ -」
平安道翠 187,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Temari - 手毬 -」
一秀 182,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Kourin - 光凛 -」
一秀 186,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Maikiku - 舞菊 -」
一秀 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「晴れの日」
柴田家千代 238,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「光の旋律」
柴田家千代 242,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「心 - kokoro -」
柴田家千代 228,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「卯楽 - ura -」
雅泉 143,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「わたしの宝物」
柴田家千代 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「逢 - au -」
柴田家千代 226,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「ma cherie - マシェリ - 京紫-」
柴田家千代 223,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「ma cherie - マシェリ - 紅赤 -」
柴田家千代 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「春の陽ざし。」
雅泉 189,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「やさしい春に。」
柴田家千代 206,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Cuore - クオーレ -」
眼楽亭富久月 横山一彦 205,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Pace - パーチェ -」
眼楽亭富久月 横山一彦 207,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「煌羅 - kirara -」
平安道翠 148,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「彩葉 - iroha -」
平安道翠 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「杏鶴 - azu -」
望月龍翠 369,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「初春 - uiha -」
望月龍翠 373,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「美煌 - mikou -」
眼楽亭富久月 横山一彦 278,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「美都 - mito -」
芳峰 275,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「妃穂 - hiho -」
小出松寿 326,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「妃澄 - hisumi -」
小出松寿 322,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「春の佳き日」
清水久遊 作 -ひいな- 366,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「雅の良き日」
清水久遊 作 -ひいな- 368,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「寿の彩 - kotonosai -」
小出松寿 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「寿の結 - kotonoyui -」
小出松寿 368,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「桜舞 - 結 -」
眼楽亭富久月 横山一彦 308,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「桜舞 - 景 -」
眼楽亭富久月 横山一彦 305,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「宝瑞 - houzui -」
眼楽亭富久月 横山一彦 308,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「宝香 - houka -」
眼楽亭富久月 横山一彦 302,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「惺羅 - seira -」
平安博翠 215,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「心季 - shiki -」
平安博翠 224,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「桜叶 - ouka -」
平安博翠 226,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「叶愛 - kanae -」
平安博翠 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Tsuki - 月 -(白木)」
眼楽亭富久月 横山一彦 251,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Tsuki - 月 -(黒)」
眼楽亭富久月 横山一彦 251,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「En - 縁 -(白木)」
眼楽亭富久月 横山一彦 248,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「En - 縁 -(黒)」
眼楽亭富久月 横山一彦 248,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Sui - 翠 -(白木)」
眼楽亭富久月 横山一彦 248,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Sui - 翠 -(黒)」
眼楽亭富久月 横山一彦 248,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Shin - 心 -(白木)」
眼楽亭富久月 横山一彦 246,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Shin - 心 -(黒)」
眼楽亭富久月 横山一彦 246,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Towa - 永 -(白木)」
眼楽亭富久月 横山一彦 251,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Towa - 永 -(黒)」
眼楽亭富久月 横山一彦 251,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
和彩 - aisa -
柴田家千代 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「奏々 - sousou -」
平安道翠 198,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「羽音の舞 - haoto -」
小出松寿 315,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「羽衣の舞 - hagoromo -」
小出松寿 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「RICH・ECLAT - リッシュ・エクラ -」
望月龍翠 346,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「RICH・LUMIERE - リッシュ・ルミエール -」
望月龍翠 346,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「桜のおはなし」
鈴木晃隆 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「森のおはなし」
鈴木晃隆 98,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「帆々雛 - ほほ -」
鈴木晃隆 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「乃々雛 - のの -」
鈴木晃隆 166,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「夢々雛 - ゆゆ -」
鈴木晃隆 136,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「咲々雛 - ささ -」
鈴木晃隆 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「希々雛 - きき -」
鈴木晃隆 148,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「心々雛 - ここ -」
鈴木晃隆 155,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「幸珠 - kouju -」
平安道翠 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「桜珠 - ouju -」
平安道翠 168,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Ivy - アイビー -」
御幸清鳳 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「Linoa - リノア -」
御幸清鳳 187,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「ひらひらきらり」
雅泉 128,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「ひらひらゆらり」
雅泉 128,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「黎美 - reimi -」
雅泉 SOLD OUT -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「花綴 - hanatuzuri -」
平安道翠 178,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「光采の儀 - こうさい -」
望月龍翠 271,000円(税込) -
 雛人形・ひな人形
雛人形・ひな人形
「光礼の儀 - こうれい -」
田村芙紗彦 276,000円(税込)
- < Prev
- Next >
雛人形 - 桃の節句に関して
桃の節句は、3月3日に行われる雛祭りのことで、雛人形を飾り、女の子の健やかな成長と幸せを願う伝統行事です。
上巳(じょうし)の節句とも呼ばれ、平安時代には人形(ひとがた)・形代(かたしろ)と呼ばれる、紙や草木でつくられた人形を川や海に流すことで厄を払い幸せを願いました。
その後、貴族の女の子たちの間で、人形を御殿の中で遊ばせる「ひいな遊び」が流行しました。
江戸時代になると、雛人形を飾るようになり、菱餅・白酒・雛菓子などを供え、祝い、会食したといいます。
雛人形には、女の子が優しく美しく育ち、将来良き伴侶に恵まれ、幸せな人生を送れるようにという願いが込められています。
よくある質問
- 雛人形はいつ頃飾るものですか?
立春(2月4日頃)から2月中旬にかけてがよいと言われています。
節分で厄を払った後に飾ると覚えやすいと思います。
また、二十四節気のうちの雨水(うすい)の日(2月18日頃)に飾ると良縁に恵まれるとも言われています。雨水とは雪が溶けて川に流れ、草木が芽生える頃で、昔から農耕の準備を始める目安とされてきました。春を迎える準備を始める時期になります。
- 雛人形はどこに飾ればよいですか?
北向きは避けて、東南(辰巳)の方角に向けて飾るのが良いと言われております。直射日光やエアコンがあたる場所は避けて皆様が楽しめる場所に飾ってください。
- 雛人形にはどんな種類がありますか?
雛人形は作りの違いで「衣裳着(いしょうぎ)人形」と「木目込(きめこみ)人形」とがあります。人間が着物を着るように、藁や桐の胴体に布地を着せ付けていく作りの「衣裳着人形」、桐塑(とうそ)と呼ばれる、桐の木の粉に糊を混ぜて粘土状にしたものに胡粉(ごふん)を塗り、溝を彫り、ヘラで衣裳を入れ込む作りの「木目込人形」とに分類されます。
飾り方のスタイルは、一段で飾る「平飾り」、三段・五段・七段と複数段で飾る「段飾り」、ガラスやアクリルで出来たケースの中に飾る「ケース飾り」に分かれます。
飾る人数で呼び方も変わります。男雛・女雛の二人の飾りを「親王(しんのう)飾り」、親王+三人官女(さんにんかんじょ)を「五人飾り」、そこに五人囃子(ごにんばやし)を加えた飾りを「十人飾り」、更に随身(ずいじん・ずいしん)や仕丁(じちょう・しちょう)を加えて「十五人飾り」と呼びます。
- 雛人形を選ぶときのポイントを教えてください。
まずはお家のどこに飾るかを決めることで、選ぶ雛飾りの大きさが絞れると思います。
飾る場所の間口(横幅)と奥行きを測り、どのくらいのスペースがとれるのか。棚やテーブルなどで長さが足りない場合は、コンパネなどの板を理想の大きさにカットして、雛飾りを飾る際にスペースを拡張することも検討されると選び方にも幅が出ると思います。
そして、サイズが決まったら、お人形を何人で飾るのかを検討します。人数別で飾り方の呼び名が違うので、「雛人形にはどんな種類がありますか?」をご参照ください。
人数が決まりましたら、衣裳着人形にするか、木目込人形にするかをお選びください。
そうしましたら、いよいよ、お顔とお衣裳です。基本的にお顔は頭師(かしらし)、お衣裳は人形師(にんぎょうし)が分業で製作しています。木目込人形はお顔をボディに固定していて、衣裳着人形は胴体にお顔を取り付けていますが、固定はされていないので、場合によってはお好みで顔を替えることも可能です。お顔もお衣裳も素材や作りによって価格は変わります。お好みの表情やお衣裳を楽しんでお選びください。
その他、お選びになる際にご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お客様の声
-
オンラインで高価な雛人形を買うことに最初は不安もありましたが、結果、サービスにも商品にも大満足です。
とても可愛らしいお雛様、気に入っています。大切にします。有難うございました。 -
永光さんのお雛様たちは背景や小物など細部に至るまで美しく作られ、素敵な組み合わせで見ているだけでも目の保養になります。
娘が独り立ちしても今回買ったお雛様を飾り、夫婦であれこれ思い出に浸る未来を想像できるくらい素敵なお人形を見つけられました。ありがとうございました。 -
娘のお雛様を購入しました。長男の兜も購入し、センスの良いものばかりでしたので第二子が誕生してからも永光さんで購入したいと決めておりました。
もし、また3人目が産まれた際も永光さんで購入しようと思うくらい素敵なお人形屋さんです。 -
一生に一度の買い物かもしれないので、実物を見に行けないのは最初不安でしたが、とても信頼できるお人形屋さんです!
とても良いお人形を見つけることができて本当に良かったです。
娘がお嫁に行っても、このお人形は置いていってほしいぐらいお気に入りなので、一生大切にしたいと思います。
※Googleのクチコミより引用